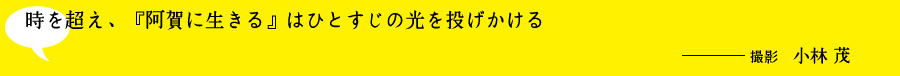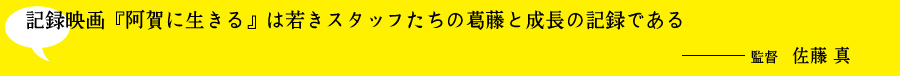|

|
|
佐藤真監督の『阿賀に生きる』は、人類のかけがいのない「現在」を未来に向けて投影する。それは、被写体となった方々の忘れがたい表情やその背後に拡がる風景の「現在」のみならず、それにキャメラを向けたスタッフ全員の「現在」をも未来に向けて投影している。あらゆるすぐれた映画が、たんなる「過去」の記録にとどまりえず、いつの時代にも貴重な「現在」としての刺激をあたりに波及させうるのは、そうした理由による。その刺激を顔一面に受けとめるために、この作品をぜひともニュープリントのフィルムで見なければなるまい。
|
|

|
|
私はこの『阿賀に生きる』を何回見たことでしょう。私の専門は河川工学・土木史ですが、この映画を見るたびに多くのことに気づかされてきました。
たとえば、あの「鉤流し」漁をどう評価するかです。竹竿につけた鉤で手探りで鮭を引っ掛ける漁法。あれほど見事な「自然との共生」の技術はないと思います。一網打尽の漁法とは異なります。腕が良くなければたくさん獲れないし、必ず獲り残しがあり、それは自然産卵し、また熊などの餌になるわけです。熊などがそれを食べ散らかせば、海のミネラルが森に散布され、森が豊かになります。
このことはカナダのトム・ライムヘン教授が15年ほど前の研究で明らかにしたことですが、鮭という字は旁に土が二つあり、中国人はもしかしたら鮭などが森の土を豊かにすることを知っていたのかもしれません。森が海を豊かにすることは、「森は海の恋人」という気仙沼から発信されたフレーズで知れ渡りましたが、その逆も有るということです。
『阿賀に生きる』では水田耕作の映像が良く出てきますが、「鉤流し」や「風の話」などは自然と共生していた「縄文人の心」が伝えられてきたものだと思います。縄文時代以来長く自然と共生してきた日本人を単純に弥生時代以降の農耕民族と決め付けることはできません。
『阿賀に生きる』は、川との共生を忘れ、川を収奪しきった近代技術の問題点をあぶり出し、もう一度「自然と共生する」なかに我われの豊かさがあることを教えてくれています。
この映画は本当に奥深いと思います。
|
|
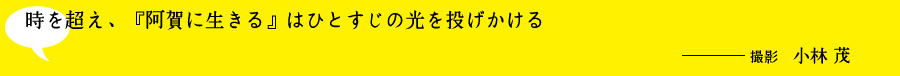
|
|
『阿賀に生きる』は、過去の映画ではなく、東日本大震災や原発爆発を経験したわれわれが生きていく世界に、ひとすじの光を投げかけているのではないだろうか。
新潟水俣病が発生した阿賀野川を舞台にしたドキュメンタリー映画『阿賀に生きる』(佐藤真監督)は、今年、完成から20周年を迎えました。若き素人集団7人が、3年間の共同生活の中からつむぎだした作品は、有志の市民による製作委員会の支えと、多くの人々のカンパによってゴールを迎えたものです。
20年前、早春のダビング作業を経て、5月に新潟市公会堂にて完成披露上映会をいたしました。登場する皆さんを招待したその日は生涯忘れることができません。
その後、新潟県内各所で先行上映会が開かれ、秋には東京・六本木シネ・ヴィヴァンで当時としては異例のドキュメンタリー映画の劇場公開がなされました。また、ニヨン国際ドキュメンタリー映画祭銀賞や山形国際ドキュメンタリー映画祭優秀賞など国内外の映画賞を多数受賞しました。
昨年の東日本大震災と東電福島第一原発の爆発以後、『阿賀に生きる』は新たな視点をもって見られているように感じます。映画に登場する人びとは自然と強く結びついた生き方をしていました。そういう人びとが公害の直撃を受け、コミュニティの破壊を体験したのです。原発崩壊の現状は水俣病が経験してきたことのようにも思えます。これからの私たちは「自然を内包した生き方」を思索し、そこに希望や未来を描くべきではないでしょうか。
『阿賀に生きる』は今もたびたび上映され、今は亡き登場人物がよみがえります。上映環境の変化からDVD上映されることもふえました。しかし今回、私たちはあえて、16mmフィルムのニュープリントを再びたくさんの人からいただいたカンパにて作成いたしました。なぜ、フィルムにこだわるのかというご意見も十分承知しながら、『阿賀に生きる』をフィルムの形で今後50年、100年と保存したいと考えたからです。
佐藤真監督が急逝して今年で5年。彼の遺影のまえで、ニュープリントで『阿賀に生きる』を上映したいと思います。
|
|
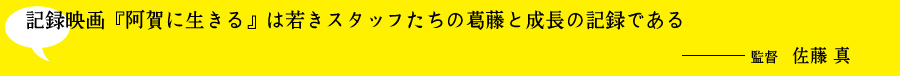
|
|
撮影を始めた時、阿賀野川は死に絶えた川だと思っていました。58もの発電所で開発し尽くされて、新潟水俣病の舞台になった川です。往時の川漁や舟運の自慢話を核に撮ればいいと、川筋を歩き始めたのです。
しかし、「阿賀の家」と名づけた川筋の家に暮らし始めてみると、阿賀野川が次第に大きく生き生きと輝き始めて見えてきました。私達の家の囲炉裏には炭がおこされ季節ごとの川魚や山の幸、川漁の自慢話が日夜賑やかに花咲くのです。長い間、同じ川を見つめ続けてくると、今まで気付かなかった川音や鳥の声、川の表情の豊かな変わりように目を見はらされます。3年の共同生活は、阿賀の豊かさを充分に体感させてくれるものでした。その中で、川筋の人々は、等しく阿賀の恩恵の中に暮らしてきたことに気づき始めました。
私達は、田んぼ仕事を手伝ったり、酒を酌み交わしながらその「暮らし」まるごとをフィルムに収めたい衝動にいつもかられていました。面白くて可笑しくてホロリとさせられる=そんな日常を丁寧に撮ることで、それを壊してきたものの残酷さがあぶり出しになればと思ってきました。
私達の映画の主役は自分の仕事と生き様に誇りを持ち続けて、見事な年のとり方をした人達です。また深く阿賀と暮らしてきた故に、一方では新潟水俣病の被害者家族でもあるのです。
この映画は、14の瞳と耳で阿賀野川を見つめ続けてきた7人のスタッフの力の結晶です。またそれは、製作委員会に集った無償の市民の無数の瞳に支え続けられた結果でありました。
そして、この3年間の記録はまた、逆に阿賀に生きる人々に見つめ返されることで変わってきた私たちスタッフ7人の葛藤と成長の記録でもあるのです。
|